第1子が6歳になった翌月がちょうど新年で区切りが良かったので、そこからお小遣いを開始しました。我が家のお小遣い制度の現状をお知らせします。
お小遣いをあげるにあたって、子どもと決めた約束を以下のように文章にしてリビングの目のつく所に張り出しています。
責任:お小遣いをもらうために、毎日決めたお手伝いをする。
金額:毎月500円。自分の欲しい物に使える。足りない分はお年玉から出す。
お年玉:1年後に残った金額に利息がつく。利息は日本国債10年変動金利に準ずる。
お菓子:500円で自分で購入する。おつりは親に返す。
誕生日:誕生日の人だけがプレゼントをもらえる。1万円を超えた場合は自分で出す。
クリスマス:全員がプレゼントをもらえる。1万円を超えた場合は自分で出す。
学校で必要なもの:自分で半分出す。自分で買うようになったらお小遣いの金額が300円増える。
それでは、詳しく解説していきます!
責任
何もしていないのにお小遣いを貰えるのはおかしいよね、ということで子どもに毎日するお手伝いを決めさせました。
お手伝いなので、自分のことではなく家族みんなのためになることにしています。
現在カーテン係とタオル係をやってくれてます。カーテンの開け閉めと、タオルはお風呂用のタオルの準備と片付けです。
金額
金額の設定は悩みましたが、無難なところで毎月500円としました。
お年玉
お金本体は子ども名義の口座に入金して触らないようにしているのですが、金額だけお小遣い張に記入して管理させています。
毎月のお小遣いで賄えない物を買いたい場合は、一旦親が立て替えて、お小遣い張のお年玉残高の額を減らしていくという方式です。
1年後の残金に利息をつけるのは、厚切りジェイソンさんがお子さん達に実践されている方法を採用させていただきました。以下の書籍を参考にしました。
利息の利率は、夫と相談して日本国債の10年変動金利にしようと決めました。
新しいおもちゃをねだられた時、自分のお金だったら買って良いよ、と言うと子どもはちゃんと自分で考え、自分のお金で買わなきゃいけないならやめる、とすんなりやめてくれる事が多くなりました。
お菓子
お菓子は、お小遣いとは別に週1程度の頻度で500円までとして、好きな物を買わせています。
セルフレジのあるお店を選んで、自分でお菓子のバーコードを読ませて現金で支払ってお釣りをもらう所までやらせています。
そして、お釣りは親に返してもらうのですが、帰宅後貯金箱に貯めています。貯まったら海洋プラスチック対策に尽力している団体に寄付する予定です。
誕生日
お小遣い制度を始める前までは、誕生日の際は他の兄妹児にも似たようなプレゼントを渡していました。おかげで羨ましくなったり、プレゼントの奪い合いなどは起こらず済んでいました。
詳しくは以下に記事にしていますので、よければそちらもご覧ください。
しかし、お小遣いを始めるにあたり、誕生日の時に本当に欲しいものを貰えた方がいいよね、兄妹の誕生日プレゼントがどうしても羨ましくて欲しかったら自分のお年玉で買おう、ということになり、誕生日の人だけがプレゼントをもらえることになりました。
上限額は1万円で、それ以上の金額分は自分のお年玉から出すことにしました。
クリスマス
クリスマスは子どもたち全員がそれぞれ欲しいものを買ってもらえるようになりました。
ただし上限額は誕生日プレゼントと同様に1万円です。
学校で必要なもの
まだ第一子は文房具にこだわりがないので親が用意していますが、今後自分で買いたがるようになった時に備えてルールは設定しておきました。
文房具を始め、学校で必要なものを自分で購入する場合は、購入金額の半分を親が負担してあげます。そうした場合、毎月500円のお小遣いでは足りないことが予想されますので、お小遣いの額も300円増額して800円になる予定です。
お小遣いが1,000円は額が少し大きいかな、と思ったので800円にしました。
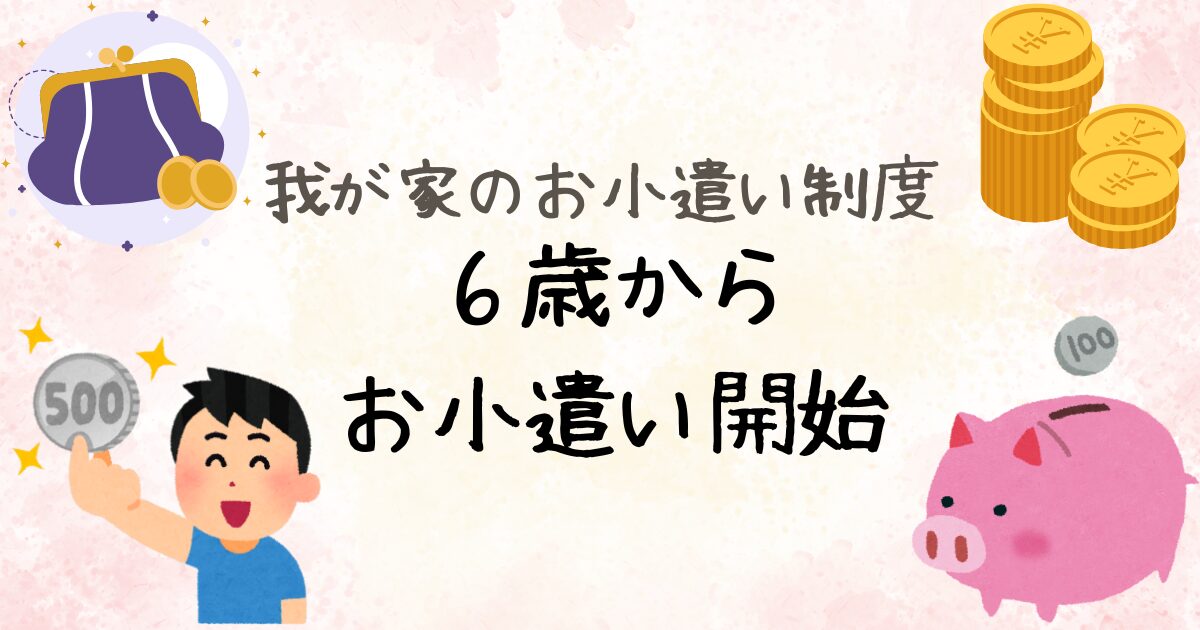

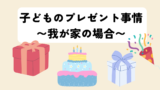
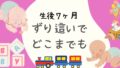

コメント